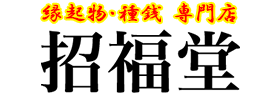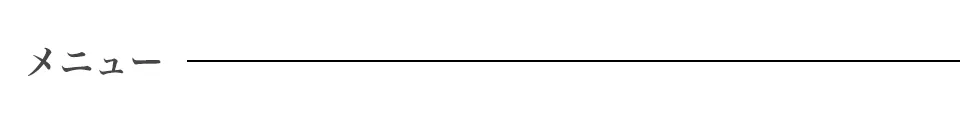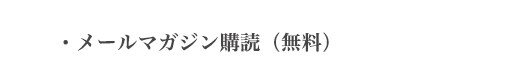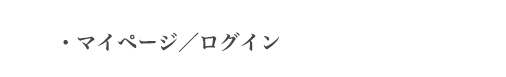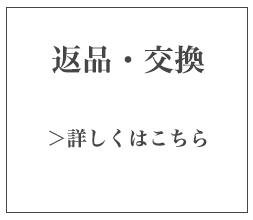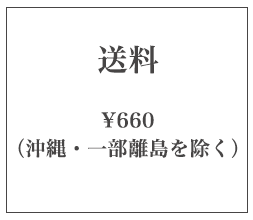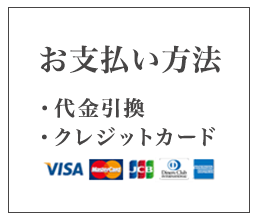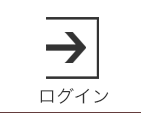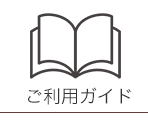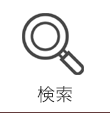馬にゆかりのある全国の神社13選|午年の参拝や絵馬祈願で開運

2026年は、十二支で「午(うま)」の年です。
「午」は馬を象徴する干支でもあり、その力強さや前進する姿から、古くから人々の信仰と深く結びついてきました。
神社で祀られたり、絵馬として奉納されるかたちで、今もその信仰は受け継がれています。
この記事では、全国の神社の中から、とくに馬と深いゆかりを持つ13社を厳選しました。
それぞれの見どころや金運・開運などのご利益を解説していますので、開運参りや旅行の計画の参考にしてください。
他に、金運や勝負運が上がる「馬」モチーフのアイテムもご紹介。
2026年の運気を大きく駆け上がりたい方は、チェックしてくださいね
\春財布に入れて金運アップ!/
PickUP!金運招福をもたらす左馬の財布お守り種銭
 |
純金万馬銭(じゅんきんまんばせん) 2026年の年賀状にも描かれた「左馬(ひだりうま)」は、古来より金運アップや商売繁盛の縁起物として親しまれてきました。 お財布や通帳に忍ばせておくことで、金運を育てる種銭として福を呼び込むお守りとなります。 |
| 詳細を見る≫ | |
北海道の馬にゆかりのある神社
馬に込められた願いや大切にされてきた思いは、今も神社で受け継がれています。
なかでも北海道は、サラブレッドの産地やばんえい競馬の舞台として知られ、馬と人との深い結びつきが息づく地域です。
ここからは、そうした信仰を今に伝える「馬とゆかりのある神社」を地域別にご紹介します。
西舎神社(北海道)|サラブレッド生産地を代表する神社

引用:うらかわ+(浦河町公式サイト)
(https://ko-ho-urakawa.com/)
北海道浦河町にある西舎神社(にしちゃじんじゃ)は、全国有数のサラブレッド産地・日高地方を代表する神社です。
毎年1月には「騎馬参拝」と呼ばれる伝統行事が行われ、JRA日高育成牧場の職員がサラブレッドやポニーに騎乗して参拝します。
境内には馬をモチーフにした奉納物や絵馬も多く見られ、競馬や牧場関係者が必勝祈願や厄除けを願って訪れます。
勝負運や馬とのご縁を求めて参拝する人も多く、日高地方の馬文化を象徴する神社として親しまれています。
- 住所:〒057-0171 北海道浦河郡浦河町西舎124
十勝輓馬神社(北海道)|ばんえい競馬ゆかりの必勝祈願で親しまれる神社

引用:とかちむら公式サイト
(https://www.tokachi-mura.com/)
帯広市にある十勝輓馬神社(とかちばんばじんじゃ)は、「ばんえい競馬」の舞台・帯広競馬場のすぐそばに建つ神社で、「とかちひきうまじんじゃ」と呼ばれることもあります。
昭和47年(1972年)に、ばん馬の安全やレースの成功を祈って建立されて以来、騎手や関係者が必勝祈願に訪れる場として親しまれてきました。
境内には力強い馬の像があり、勝負運を願う受験生やスポーツ選手が参拝することもあります。
授与品として、輓馬神社オリジナルの絵馬やおみくじ、お守りなどが用意されており、競馬関係者だけでなく、一般の参拝者からも人気です。
北海道の開拓とともに歩んできたばんえい競馬の歴史を感じられる場所として、今も多くの人に大切にされています。
※ばんえい競馬:北海道開拓期の1900年頃、農耕馬の力を競う「ひき馬」が起源とされ、現在も公営競技として行われています。
体重1トン前後のばん馬が最大1トンの鉄そりを引いて200メートルの直線コースを進みます。
- 住所:北海道帯広市西13条南8丁目1
東北地方の馬にゆかりのある神社
東北には、暮らしや歴史の中で馬と深く関わってきた神社が残っています。
今も地域に根づく信仰として受け継がれ、行事や祭りを通してそのつながりを見ることができます。
水沢駒形神社(岩手県)|駒形信仰の総本宮として馬とのつながりを伝える神社

引用:水沢駒形神社 公式サイト
(https://komagata.iwate.jp/)
岩手県奥州市にある「陸中一宮 駒形神社(通称:水沢駒形神社)」は、全国に30余社ある駒形神社の総本宮です。
奈良時代・天平年間(8世紀)に創建され、古くから馬を守る神様として信仰されてきました。
かつては農作業や運搬、戦で活躍した馬の安全や力を願う場所として親しまれ、現在も家内安全や商売繁盛、産業の発展を祈って多くの人が参拝に訪れます。
毎年5月5日に行われる例大祭「駒形祭」では、勇ましい流鏑馬神事(やぶさめしんじ)が奉納され、地域と馬との深いつながりを今に伝えています。 東北を代表する「馬の神社」として、金運祈願に訪れる人の姿も多く見られます。
- 住所:岩手県奥州市水沢中上野町1-83
- URL:水沢駒形神社(陸中一宮 駒形神社)
https://komagata.iwate.jp/
関東地方の馬にゆかりのある神社
関東には、ご神馬と触れ合える神社や、競馬とゆかりの深い神社があり、多くの人に親しまれています。
五方山 熊野神社(東京都)|3頭のポニーが迎える、競馬ゆかりの神社

引用:五方山 熊野神社 公式サイト
(https://jinjya.kumano-kids.com/)
葛飾区にある五方山熊野神社は、平安時代中期に創建された、陰陽師・安倍晴明にゆかりのある神社です。
境内にはご神馬として3頭のポニーが大切に飼育されていて、併設された幼稚園の子どもたちと触れ合ったり、七五三では馬車を引いたりと、参拝者に癒やしを与える存在になっています。
宮司は騎手や調教師の家系に生まれ、自身も日本中央競馬会(JRA)の元職員という異色の経歴を持ちます。
競馬との深い縁が息づく、全国的にも珍しい神社です。
- 住所:東京都葛飾区立石8-44-31
- URL:五方山熊野神社
https://jinjya.kumano-kids.com/
中部地方の馬にゆかりのある神社
中部地方には、かつて人々の暮らしを支えた馬と深い関わりを持つ神社が今も伝わっています。
農耕や祭礼と結びついた歴史を持ち、五穀豊穣や地域の繁栄を願う場として大切にされてきました。
日長神社(愛知県)|飾り馬の奉納で五穀豊穣を祈る古社

引用:知多市観光ガイド
(https://chita-kanko.com/spot/detail/60/)
愛知県知多市にある日長神社は、平安時代の「延喜式」に名が記される由緒ある神社です。
毎年春に行われる「日長の御馬頭(おんばとう)」では、42歳の厄年の男性たちが、美しい馬具をまとった献馬(けんば)を引き、参道を往復して奉納します。
標具(だし)と呼ばれる札や御幣を飾った飾り馬を捧げ、五穀豊穣や雨乞いを祈願する伝統行事で、市の無形民俗文化財にも指定されています。
もともとは農作業を支える馬の健康と安全を祈る神社として信仰されてきましたが、今では交通安全や厄除けを願う人々も多く訪れます。
また、境内には紅葉スポット「紅葉谷(もみじだに)」があり、11月下旬から12月にかけて見頃を迎える紅葉まつりの時期には参拝客で賑わいます。
- 住所:愛知県知多市日長森下4
関西地方の馬にゆかりのある神社
古くから武運や豊穣を願って馬とともに祈りを捧げてきた歴史があり、関西にもその信仰を今に伝える神社が点在しています。
競馬発祥の地とされる社や、絵馬の風習が生まれた神社など、馬との深い関わりが感じられる神社をご紹介します。
許波多神社(京都府)|勝運の神と競馬ゆかりの「馬の神社」

引用:京都宇治観光マップ
(https://travel.ujicci.or.jp/app/public/shop/index/137)
京都府宇治市にある許波多神社(こはたじんじゃ)は、大化元年(645年)に創建された歴史ある神社です。
皇位継承をめぐる壬申の乱の際には、大海人皇子(のちの天武天皇)が戦勝を祈願し、坂上田村麻呂も東征の際に武運を祈ったといわれています。
こうした由来から「勝運を授かる神社」として信仰されてきました。
また、競馬発祥の地とも伝わり、かつては社殿から続く東西2町の馬道で「くらべうま」の神事が行われていました。
さらに、社宝の神像が馬頭を戴いていることから「馬の神社」としても知られ、競馬関係者やファンの参拝も多い神社です。
- 住所:京都府宇治市五ケ庄古川13
- URL:許波多神社 公式インスタ
https://www.instagram.com/kyotouji_kohatajinja.official/
貴船神社(京都府)|絵馬発祥の地で縁結び・金運祈願

京都市左京区にある貴船神社は、水の神さま・高龗神(たかおかみのかみ)を祀る歴史ある神社です。
かつては雨を願うときに黒馬、晴れを願うときに白馬を奉納していたことから、やがて木の板に馬の絵を描いて捧げる「絵馬」の風習が生まれたといわれています。
境内には今も多くの絵馬が並び、縁結びの神社として知られるほか、商売繁盛や金運を願って参拝する人も多く訪れます。
また、歴史ある神社として、観光を目的に足を運ぶ人の姿も見られます。
- 住所:京都府京都市左京区鞍馬貴船町180
- URL:貴船神社 公式サイト
https://kifunejinja.jp/
春日大社(奈良県)|競馬・流鏑馬ゆかりの馬出橋が残る神社

引用:春日大社 公式サイト
(https://www.kasugataisha.or.jp/)
奈良市にある春日大社は、768年に神山・御蓋山(みかさやま)の麓に平城京の守護と国民の繁栄を祈って創建された由緒ある神社です。
1998年には「古都奈良の文化財」として世界遺産にも登録されています。
一之鳥居から萬葉植物園前へとまっすぐに延びる表参道は、かつて競馬や流鏑馬が行われた馬場だったと伝えられています。
その起点となる「馬出橋(まだしのはし)」は、今でも春日若宮おん祭の競馬が出走する場所として知られて
平安時代の歴史書「貞観儀式」や貴族の日記「権記」「御堂関白記」にも、春日祭で走馬や競馬(くらべうま)が奉納された記録が残されており、古くから馬と深く関わってきた歴史を感じられます。
- 住所:奈良県奈良市春日野町160
- URL:春日大社 公式サイト
https://www.kasugataisha.or.jp/
中国地方の馬にゆかりのある神社
中国地方には、古くから馬とともに歩んできた歴史を伝える神社が点在しています。
今も流鏑馬(やぶさめ)や競馬神事などの伝統行事が受け継がれ、五穀豊穣や必勝祈願の場として多くの人が参拝しています。
鷲原八幡宮(島根県)|流鏑馬の舞台で勝負運祈願

引用:しまね観光ナビ
(https://www.kankou-shimane.com/destination/20642)
島根県津和野町に鎮座する鷲原八幡宮(わしばらはちまんぐう)は、1387年に石見国地頭・吉見頼直が鶴岡八幡宮から八幡神を勧請し、1405年に現在地へ遷座したと伝わる歴史ある神社です。
津和野川のほとりに残る流鏑馬馬場は中世の姿を今に伝え、国の重要有形民俗文化財にも指定されています。
毎年4月に行われる「流鏑馬神事(やぶさめしんじ)」では、馬上から矢を放ち五穀豊穣や安全、必勝などを祈願します。
日本三大流鏑馬の一つに数えられる伝統行事で、迫力ある神事を目当てに多くの参拝者や観光客が訪れます。
- 住所:島根県鹿足郡津和野町鷲原
大浦神社(岡山県)|伝統の競馬神事が続く海辺の神社

引用:大浦神社 公式サイト
(https://www.oourajinja.com/)
岡山県浅口市寄島町にある大浦神社は、瀬戸内海を望む高台に鎮座する歴史ある神社です。
毎年秋の例大祭では「競馬神事(けいばしんじ)」と呼ばれる伝統行事が行われ、境内に設けられた馬場を馬が駆け抜け、豊作や地域の安全を祈ります。
かつては40頭もの馬が奉納された歴史があり、馬との深い関わりがこの地に根づいています。
本殿や拝殿、鳥居は国の登録有形文化財に指定され、長い歴史とともに地元の人に大切にされてきました。
- 住所:岡山県浅口市寄島町7756番地
- URL:大浦神社 公式サイト
https://www.oourajinja.com/
.四国地方の馬にゆかりのある神社
四国には、動物の「馬」ではなく、「よさこい節」に登場する人物・お馬を祀った神社があり、今も地元の人に親しまれています。
お馬神社(高知県須崎市)|よさこい節ゆかりの「お馬」を祀る縁結びの神社

引用:奥四万十時間
(https://okushimanto.jp/)
高知県須崎市にあるお馬神社は、「土佐の高知のはりまや橋で〜」の歌詞で知られる「よさこい節」に登場する人物・お馬を祀った神社です。
お馬は僧・純信と駆け落ちしたものの連れ戻され、その後この地で結婚して約30年を過ごしたといわれています。
神社は「縁結びの神様」として知られる二股杉の下に建てられており、良縁を願って訪れる人の姿も見られます。
- 住所:高知県須崎市須崎
九州地方の馬にゆかりのある神社
九州には、昔から馬とのつながりを大切にしてきた神社があり、今も交通安全や合格祈願などさまざまな願いを込めて多くの人が参拝しています。
宇賀神社(福岡県福岡市)|「落ちない馬形」で合格祈願としても人気

引用:神社人
(https://jinjajin.jp/modules/newdb/detail.php?id=8360)
福岡市中央区大宮にある宇賀神社は、宇賀魂神(うがたまのかみ)を祀る神社です。
穀霊の神として豊かさや福をもたらすとされ、地域の人から親しまれてきました。
2005年の福岡県西方沖地震では、鳥居が倒れるほどの被害を受けましたが、拝殿に飾られていた馬の人形(馬形)は落ちることなく無事でした。
この出来事から「落ちない」「うまくいく」として受験生の合格祈願スポットとしても注目されています。
- 住所:福岡県福岡市中央区大宮2-2
下馬神社(熊本県熊本市)|馬を降りて参拝した伝承が残る天満宮

引用:神社人
(https://jinjajin.jp/modules/newdb/detail.php?id=8011)
熊本市中央区横手にある下馬神社(げばじんじゃ)は、正式には「横手天満宮」「横手菅原神社」と呼ばれる天神さまです。
戦国時代、隈本城主・鹿子木寂心(かのこぎじゃくしん)が社前で馬が動かなくなり、下馬して参拝すると進むようになったという逸話から「下馬神社」と呼ばれるようになりました。
かつては社前を通るときに馬を降りて歩く風習もあったそうです。
主祭神は菅原道真公で、境内には神馬像が奉納されています。
現在は学業成就のほか、交通安全や厄除けを願って多くの人が参拝に訪れる、地域ゆかりの神社です。
- 住所:熊本県熊本市中央区横手1-13
午年の干支の意味と由来
馬は古くから人々の暮らしを支える存在で、その行動力や生命力から「前進」「繁栄」「活力」をもたらす象徴とされています。
そのため、午年は新しい挑戦や転機に縁起が良い年といわれています。
「午(うま)」は十二支の七番目にあたる干支で、もともとは時間や方角などを表す記号でした。
太陽が最も高く昇る「正午」に由来し、勢いよく物事が進む象徴とされています。
やがてこの「午」に、力強く前へ進む動物・馬のイメージが重ねられ、「午=馬」と結びつくようになりました。
神と馬の深い関わりと絵馬のはじまり
日本では昔、馬は神様と人とをつなぐ神聖な存在でした。
力強く速く走る姿が「願いを神のもとへ届けてくれる」と信じられ、神事や祭礼でも欠かせない役割を担っていました。
雨を願うときは黒毛の馬、晴れを望むときは白毛の馬を奉納するなど、祈りの内容に応じて毛色を選ぶ習わしもありました。
しかし、本物の馬を奉納し続けるのは大きな負担となったため、次第に木や石で作られた馬像や、馬を描いた板が代わりとして奉納されるようになりました。
これが「絵馬」の始まりです。
今では受験や合格祈願、縁結び、金運など、さまざまな願いを込める手段として広く親しまれていますが、その起源は京都の貴船神社といわれています。
馬が縁起物とされる理由
神様への祈りを届ける存在として大切にされてきた馬は、人々の暮らしの中でも欠かせない存在でした。
田畑を耕し、荷物や人を運び、移動手段として役立ったことから「豊かさ」や「繁栄」をもたらす象徴とされ、戦では力強さと俊敏さで勝敗を左右する存在として「勝負運」や「勇気」と結びつけられてきました。
また、馬は神話や伝承の中では神と深く関わる存在として描かれることも多く、「運を呼び込む象徴」としても信じられてきました。
こうした背景から、馬は金運や成功、家内安全など幅広い幸運をもたらす縁起物として現在でも親しまれています。
馬をかたどった置物やお守り、馬蹄(ばてい)モチーフのアクセサリーなどを身につけることは、運気を高める縁起担ぎとして人気があります。
午年におすすめ。馬モチーフのアイテム
古くから馬は、人々の暮らしを支え、神への祈りを届ける特別な存在として大切にされてきました。
豊かさや繁栄、勝負運など、さまざまな幸運を運ぶ象徴とされてきたその力は、今も神社での信仰や絵馬の奉納、そして縁起物としての文化の中に息づいています。
2026年の午年は、「前進」「飛躍」を意味する節目の年です。
そんな年には、馬とゆかりのある神社への参拝で新たな運気を迎えるのはもちろん、馬蹄(ばてい)モチーフのアクセサリーや「左馬(ひだりうま)」の種銭など、馬にちなんだ縁起物を暮らしに取り入れてみるのがおすすめです。
日々の生活の中で前向きなエネルギーを呼び込み、新しい一年を力強く歩んでいく後押しとなってくれるでしょう。
Pickup!馬のご神徳を手元に。 繁栄を授ける純金左馬
純金万馬銭(じゅんきんまんばせん)
「左馬(ひだりうま)」は、馬の字を反転させた特別な文字で、古来より商売繁盛や千客万来の縁起物として親しまれてきました。
馬を逆から読むと「舞う」となり、喜びや福を舞い込ませる吉兆。さらに「左から乗ると転ばない」といわれ、安泰のしるしとされています。
その縁起を純金に刻んだのが「純金左馬種銭」です。将棋駒をかたどり、表に左馬、裏に金の文字を彫り込むことで「財を呼び込み守り抜く」祈りを込めました。
馬にゆかりある神社へ参拝の際に携えるお守りとして、また日常で財運と繁栄を願う御守りとしてもふさわしい逸品です。
価格:58,300円(税込)
商品ページで詳しく見る≫